「青年海外協力隊はやめとけ」と言われる理由
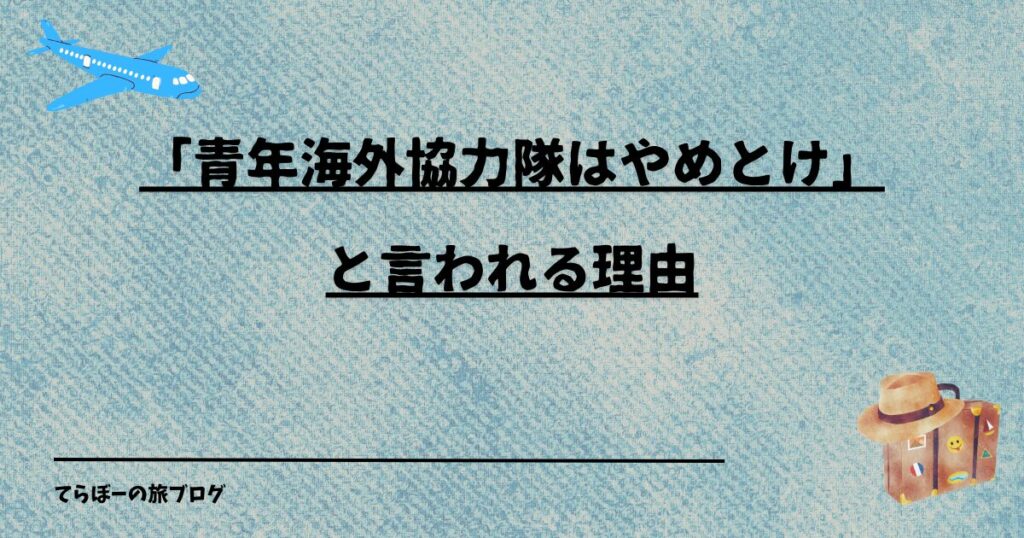
<コラム第13回:「青年海外協力隊はやめとけ」と言われる理由>
「青年海外協力隊」とウェブ検索すると、必ずトップの予測入力候補に出てくるワードが“やめとけ"である。検索結果には、協力隊への批判とそれに対する擁護のページがずらりと表示される。
協力隊経験者の私としては、どちら側の声も間違ってはいないと思う。不思議なのはなぜこんなにも長い間、協力隊に対するこうした議論が出るのかだ。私の協力隊経験とその時感じたことをもとに、考えていきたいと思う。
理由①理想と現実のギャップ
「やめとけ」と言われる最大の理由は、協力隊志願者が抱く「理想的な協力隊」と実際に行ってみて感じる「現実」のギャップが大きすぎる点だと思う。
協力隊の志願者の中には、「途上国で奮闘する協力隊がカッコいいと思ったから」とか「途上国の発展に寄与したいと思ったから」とありがちな志望理由を話す人も多い。
もちろんこれは素晴らしい理由だと思うが、実際のところ志願者が思い描いている理想とはかなりのギャップがあることは間違いない。
中でも最も多くの協力隊が抱くギャップは「現地の人に日本人ボランティアは必要とされていない」という点だ。協力隊案件は現地の人から求められて要請されると思われがちだが、実際は違う。
どちらかというと、まず大枠の案件数が各国で決められ、現地のボランティアコーディネーターがその案件数分の要請を現地の中で探しに行くという営業型方式が多い。もちろん中には、コネクションを伝ってJICAにボランティアの問い合わせをしてくる現地団体もあるが、多くの場合は「人件費無償の働き手を採用したい」という意図だ。
JICAとしても協力隊の実績を外交上のカードとする以上、ボランティア事業の目的をしっかりと伝えないまま、現地団体の要請を簡単に受理してボランティアを派遣してしまうことは多い。中には安全面や派遣目的をしっかりと練らないまま要請されていることも多い。
だから、JICA海外協力隊の募集時に掲載される要請の中には水や電気が安定していると書かれていたとしても、実際は全くインフラが整っていない場合も多いのだ。

私自身も、初日に意気揚々と派遣先に行ったら「新しいインターン」と紹介されたことがあった。残念ながら現地の人にとって、JICAボランティアはその程度の認識だ。実際に働いてみても、ただ会社の労働力として仕事をさせられたり、要請書に記載のあった仕事を全くさせてもらえなかったり、JICAが表面上話すこととの違いはとても大きい。
中には「なにしに来たの」と言われたり、まったく仕事がなくて一日中暇しているボランティアもいるようだ。しかも、こうした状況でJICAは何もしてくれない。派遣先に注意してくれることもないし、逆にさぼっていてもそれは隊員の自由だ。
こうした状況もあって、「途上国に貢献した」と言えるような結果を出せる隊員はほとんどいない。ボランティアとはいえ莫大なODA予算を費やしているにもかかわらず、投資対効果は著しく低いと言わざるを得ない。
この分の予算を円借款やインフラ投資に回した方がいいのではと思ってしまうが、ボランティアとして活動する以上、こうした事情があっても受け入れざるを得ないのが現実だ。
実際にこうしたギャップを感じて、途中で任期短縮して帰国する隊員も少なくない。だから、これから協力隊を目指すのであれば、こうした現実を受け入れたうえで派遣されるとギャップが少ないと思う。

理由②キャリア形成への弊害
JICA海外協力隊はボランティアという性質上、高額な報酬をもらえるわけではない。また、ほとんどの要請は約2年と長い。
若者にとって貴重な2年間をボランティアに費やすというのはなかなか勇気のいることだ。例えば民間企業で働く人にとってはその期間に昇進や昇給を逃すことになるし、その間に経験できるはずだった仕事やコネクションを捨てることにもなる。
実際に私も帰国して元の会社に戻ったら、多くの同期は自分より上の役職に就いていたし、「ビジネス」という観点においては2年間異国でボランティアをしていた私よりも難易度が高く汎用的な仕事の経験をしていた。
私自身は協力隊に行ったことを全く後悔していないが、ずっとこの会社で働くと仮定した場合、キャリア形成という面で停滞したことは間違いない。
その後私は転職をしたが、転職活動においても協力隊経験が必ずしも評価されるわけではないということも非常に実感した。面接では協力隊経験よりも1社目のコンサル経験のほうが興味を持たれたし、アフリカでの経験はアイスブレイクで使える程度だった。
自分のキャリアを考えたときに、協力隊に行くべきか、また協力隊に行くタイミングはいつが適切なのか、しっかりと考えたうえで応募することを推奨する。

理由③健康と安全
最後の理由は、健康と安全だ。多くの方が想像するように派遣される国のほとんどは日本よりも治安が悪く、医療へのアクセスが悪い地域だ。
治安に関しては、夜に出歩けなかったり、昼間でもタクシーが必須の地域もある。移動の自由が制限されることはもちろん、精神的にも危険を感じながら気を張って生活するのは想像以上にストレスになる。
時には同僚さえも金をせびってきたり、人種差別をしてくることも多く、一時も気が休まらない。特に女性はセクハラの標的にされたり、イスラム圏では制約が多かったりする。
医療においては、多くの隊員が生活する地方で特に酷い。診察はもちろん、必要な薬すら取得するのは難しい場合がある。重病やケガでは首都の大きい病院を受診することができるが、そこまでの移動費が自費だったり、移動時間が非常に長いこともある。
基本的に協力隊は自力で何とかすることが必要なので、JICA職員のようなJICAからの手厚いサポートを受けることはできない。自分の身は自分で守る難しさは行ってみないと分からない理想とのギャップだと思う。

このようにJICA海外協力隊には想像以上に苦労が多い。派遣される隊員の親としては、子供をこうした場所に送るのは非常に不安だと思う。
だから協力隊を経験した私自身「やめとけ」という人の気持ちも理解はできる。しかし、途上国の人々と密接にかかわることができる協力隊ならではの経験も非常に有意義なものだ。
これまでに述べたギャップを十分に理解したうえで、協力隊への応募を考えてほしいと思う。

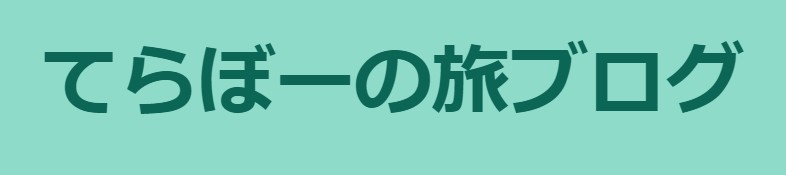




















































































































































































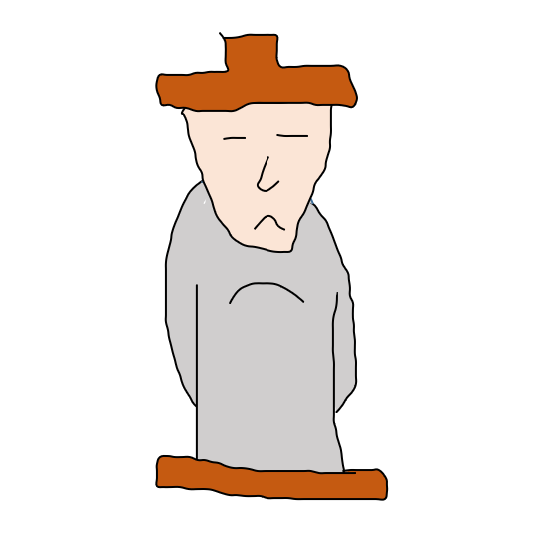
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません